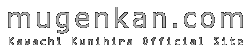62号から
「伝える熱意」と「伝わる心」
| 関西大学博物館 次長(学芸員) 熊 博毅 |
 「河内先生の授業がたいへん印象に残りました。日常生活で触れることのない刀剣を実際に解体し、手入れをしたことがとても新鮮でした」「面白
く、また恐くもあった。『人に傷が入っても治るけど、刀は直らない』とおっしゃった言葉が深く、忘れられない」「実際の刀剣を見たのも触るのも初めてで、
実物がこんなに重く、きれいなものであることに感動し、おもしろかった」「今では日本刀は私にとってなくてはならないものになり、心の支えです。
日本刀の実習で、美と用のバランスに魅かれたのが最大の理由です」 「河内先生の授業がたいへん印象に残りました。日常生活で触れることのない刀剣を実際に解体し、手入れをしたことがとても新鮮でした」「面白
く、また恐くもあった。『人に傷が入っても治るけど、刀は直らない』とおっしゃった言葉が深く、忘れられない」「実際の刀剣を見たのも触るのも初めてで、
実物がこんなに重く、きれいなものであることに感動し、おもしろかった」「今では日本刀は私にとってなくてはならないものになり、心の支えです。
日本刀の実習で、美と用のバランスに魅かれたのが最大の理由です」これらは平成二十四年度末、関西大学の博物館実習受講生に行った授業評価アンケートで「印象に残った授業とその理由を教えてください」という質問に対する回答の一部である。 関西大学では、博物館や美術館などで働く専門職である学芸員資格取得のための課程を設けており、毎年六十人ほどの学生が受講している。課程の総 仕上げとして博物館実習を受講することになっており、そこではさまざまな資料の扱い方や調書の取り方、展示の仕方、展示解説のノウハウ、写真撮影や図録作成などのほか、いくつかのチームに分かれて実際に企画展示まで行 う。学芸員が日常的にこなしている実務を、身をもって体験、修得する授業なのである。 今年はあわせて二十一人の講師が交代で専門とする分野の授業を行い、河内先生にも日本刀に関する講義をお願いした。 先生は日本刀の歴史から作刀の流れ、観賞のポイントなどを話されたあと、学生それぞれに日本刀を手に取らせ、手入れをさせたのである。 ほとんどが刀を手にするのは初めてという学生たちが手入れまで行うのである。これほどインパクトがあり、贅沢な授業は、そうそうお目にはかかれないだろう。学生たちの驚きは、いかばかりのものであったか。それが冒頭の感想文となって現れたのである。 その結果、今年は授業評価アンケートにも大きな変化が起こった。 これまで例年、最も印象に残った授業は「茶室での資料取扱いと観賞」だったのであるが、今年はこれを大きく引き離し、河内先生の「刀剣取扱いの基礎と方法」と回答した学生が最も多かった。  さらに、学生には実習レポートの提出も義務づけられている。そのなかで、ある学生は「実習で得たもの」と題し、次のような文章を綴った。
「……素直に日本刀に惚れて……その魅力にひき寄せられてか、日本刀の授業が始まったときからずっと今でもいつの日か河内國平先生のもとで刀と魂を打ち込みたいと考えています」。 さらに、学生には実習レポートの提出も義務づけられている。そのなかで、ある学生は「実習で得たもの」と題し、次のような文章を綴った。
「……素直に日本刀に惚れて……その魅力にひき寄せられてか、日本刀の授業が始まったときからずっと今でもいつの日か河内國平先生のもとで刀と魂を打ち込みたいと考えています」。見学実習で東京の博物館へ行き、そこで日本刀を見た瞬間、日本人でよかったと清々しい気持ちになったとしるしたあと、記述はさらに続く。 「ここで不思議に思うのが、日本刀には霊力的な何かがあるのでは、ということです。日本刀にはうまく言語化できない 魅力があるなと思うたび、いますぐにでも河内先生のもとへ赴きたくなります」。 実は、このレポートを書いたのは、女子学生である。これでは、まるで日笠優さんの漫画『カナヤゴ』の主人公かなみではないか。 くだんの女子学生の将来がどうなるかは別として、私はこのレポートを読んで、若い人たちに刀の魅力、伝統文化のすばらしさを伝えようとする河内先生の真剣な気持ちは間違いなく伝わっていると感じた。 若者が自国の文化を見失っているのは、単にそれに触れる機会を与えられていないからだという意見がある。確かに、 そうかもしれない。しかし、きちんと教えられ、観る機会や感じるときを与えられれば、それを受け止め、自分のものにする者は確実に存在する。想いは、心は、伝わるのである。今の若者もまだまだ捨てたものではないぞ、というのがここ数年、博物館実習の授業の一部を担当していて感じることである。 一方、博物館の現場で働く学芸員であっても、刀の扱いを知らない者は多い。こうした現状に対し、河内先生は学芸員や同好の人たちを集めた研究会の立ち上げを強く提唱され、今年から関西大学博物館が中心となり、そうした会の発足を検討している。 そして今、関西大学博物館は、平成二十五年六月から一カ月半にわたって先生の刀剣の企画展を開催すべく、その準備を進めている。 会期中には先生の列品解説のほか、講演会なども予定している。 先生の「伝えようとする熱意」が、研究会や展示会の会場へ来られた方たちにどのように伝わっていくのか。それを見るのが今の私にとって新たな楽しみとなっている。 |