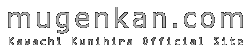56号から
おならと刀
| 阿川佐和子 |
 十年以上昔、ある地方都市で文化会議が開かれた。日本の工芸、美術、芸能などの維持発展を図ることが目的の集まりで、
歌舞伎役者や能楽師、工芸職人、芸術家、経済人などが全国各地から集まって、講演やトークショーなどを通して親睦を深めるというものだった。
そのとき私はトークショーの司会を務めたか、あるいはただ傍聴にいっただけだったか、定かな記憶はない。いずれにしてもその会議の打ち上げ立食パーティで、
テーブルに並んでいた料理を物色していたときふと、見るからに愉快そうなグループと目があった。 十年以上昔、ある地方都市で文化会議が開かれた。日本の工芸、美術、芸能などの維持発展を図ることが目的の集まりで、
歌舞伎役者や能楽師、工芸職人、芸術家、経済人などが全国各地から集まって、講演やトークショーなどを通して親睦を深めるというものだった。
そのとき私はトークショーの司会を務めたか、あるいはただ傍聴にいっただけだったか、定かな記憶はない。いずれにしてもその会議の打ち上げ立食パーティで、
テーブルに並んでいた料理を物色していたときふと、見るからに愉快そうなグループと目があった。「お皿、ここにありますよ」 「あー、どうも。このサラダ、おいしいよ」 見知らぬ者同士ながら一言二言交わしただけで、なぜか恋の花咲く…まではいかないけれど、なんだかこの人たち、面白そうだなあと、 直感的に思った。以心伝心。アチラもそう感じてくださったのか、「もう一杯、どっかで飲みましょうか」「いいですねえ、行こう行こう」 というノリのまま、宿泊ホテルの最上階のバーに赴いた。そのうちのお一人が、大阪弁バリバリの河内國平さんだったのである。 その晩、河内さんと何の話をしたのやら。そもそも「刀鍛冶」などという職業の人に会ったのは初めてで、最低限、刀を作る鍛冶屋さんぐらいの認識はあったけれど、 それ以上の技術的な話はとんと知識がない。その場にもう一人、「河内さんが作った刀に彫りを入れる」という岡山の刀身彫刻家、柳村仙寿さんもいらして、 お二人であれやこれやと私に説明してくださるが、ふうーん、へえーと感心するばかりで「大変なお仕事なのね」くらいの理解しかできなかったと思う。にもかかわらず、 お二人はおよそ権威や名声とは無縁のごとく(本当は無縁じゃないのに)、まるで気さくな関西のおっちゃんで、初対面とは思えぬ楽しい酒宴のひとときを過ごすことができた。 そして数日後、拙宅に葉書が届いた。 「あなたがテレビに出ている人とはちっとも知らず、ウチに帰って家内に叱られました。でもこれもご縁。一度、奈良の仕事場に遊びに来てください」 叱られるべきは私のほうだが、いずれにしても、互いに「どこの誰やら」よくわからずに仲良くなってしまったというわけだ。だからこそだか知らないが、 以来、私にとって河内さんは、肩書きや立場や業種を越えて、いつお会いしても、いつお声を聞いても無性に嬉しくなる、人生の大事な友となっている。 そこまで大事な友と思うわりに、そんなに大事にしていない。その証拠に、「仕事場に遊びに来てください」とお誘いいただいて、その言葉に応えたのは、 ようやく今年の夏になってからのことである。同行者は、長年、河内さんを応援し続けておられる虎屋黒川の社長夫妻とそのご友人たち。そこへ私も加えていただいた。 奈良は東吉野の山奥に到着するなり、「やあやあ、どうも」 河内さんがいつもの調子で気さくに出迎えてくださるかと思っていたら、 奥様がにこやかに、かつ厳粛なる顔で、「どうぞこちらへ。中に入ったら静かにお願いします」  まるで、すでに演奏が始まったコンサート会場へ遅刻客を誘導する案内人のように、私たちを、黒幕に包まれた真っ暗闇の小屋の中へ招き入れてくださった。 まるで、すでに演奏が始まったコンサート会場へ遅刻客を誘導する案内人のように、私たちを、黒幕に包まれた真っ暗闇の小屋の中へ招き入れてくださった。鋼を叩く。その作業の様子は写真や映像で見知っていたつもりだが、これほど迫力と崇高に満ちたものとは思いもよらなかった。驚愕した。 静かにしなければならないと意識する前に、呆然として言葉が出なかった。河内さんのいつものニコニコ顔は炎の前で別人のように引き締まり、 ときどき「よっし!」「来い!」と叫ぶ声には、思わずこちらも背筋が伸びる。何より真っ赤に燃えた鋼を炎から引き出して、いよいよ鍛錬の瞬間が訪れたときの衝撃は、 思い出すだに興奮して鳥肌が立つほどだ。静かに唸る鞴(ふいご)の音から一変、「よし!」という親方の合図とともに、 重い向槌を天に向けて振り上げる弟子の腕と背のみごとな曲線、向槌を振り下ろした瞬間の、逃げ出したくなるほどの爆発音、飛び散る火の粉、カーン、コーンと、 隣の山の彼方まで響きわたるような透き通った鉄の音。親方と弟子のみごとなあうんの呼吸を見守るうち、いつしか目頭が熱く(本当に暑かったけれど)なった。 数時間にわたる闘いを終え、涼やかで明るい戸外へ出てきた河内親方の白いシャツを見れば、まあ、穴ぼこだらけである。「火の粉でね、焼けちゃってね」 厳しい職人の顔は瞬く間に、いつもの人なつこい笑顔に戻る。 「じゃ、ちょっとシャワー浴びてきますんで、それから食事、出かけましょか」 ご子息の運転する車に乗って、いざ料理屋さんへ。その道中、刀の話や日本文化や人間を育てることについてなど、さまざま教養高き話題に会話が盛り上がりながら、 突然、僕のおじさんは、な。いつでも自在におならすんねん。それが上手やで。プッププップて、器用に放(こ)き分けるねん」 どうしてそういう話になったのか。相手が私だから話したくなられたのか。わからないけれど、私はそのとき心の底から思った。 この人、好きだ。大好きだ。仕事場での厳しさに溢れた闘う職人のまなざし。技を極めるためには努力を努力とも思わぬ心意気。 そしておなら話を唐突に始める力の抜けた大阪のおっちゃん顔。すべてを併せ持つ河内國平さんという人は、たぐいまれなる日本の宝である。 |