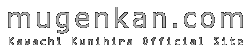55号から
大坂城南部で発見された豊臣期の鍛冶工房跡
| 大阪文化財研究所学芸員 |
| 大庭重信 |
 大阪市難波宮跡・大坂城跡の発掘調査で、今年の四月に発見された豊臣期の鍛冶工房についてご紹介します。 大阪市難波宮跡・大坂城跡の発掘調査で、今年の四月に発見された豊臣期の鍛冶工房についてご紹介します。調査地は中央区森ノ宮中央二丁目、難波宮が立地する上町台地の東斜面にあたり、現在の大阪城公園の南隣に位置します。工房跡は地下約三・五mで発見され、出土遺物や地層の年代から、慶長三(一五九八)年から同二十(一六一五)年までの間でも後半の、豊臣秀頼の時代のものと考えられます。 工房は東西十五・〇m、南北三・六mと東西に長く、上には簡単な覆屋があったようです。建物の南東側は、鉱滓や炭などの捨て場となっていました。工房の内部は東西に三つの区域に分かれており、各区には鍛冶炉が二基ずつ、合計六基見つかりました。  一部の炉には羽口が設置された状態で残されており、これによりフイゴの設置場所が復元できます。また、炉の一つのそばには、フイゴと羽口をつなぐ送風
管と考えられる中をくりぬいた竹筒が置かれていました。 一部の炉には羽口が設置された状態で残されており、これによりフイゴの設置場所が復元できます。また、炉の一つのそばには、フイゴと羽口をつなぐ送風
管と考えられる中をくりぬいた竹筒が置かれていました。各区の中央には作業空間と考えられる堅く踏みしまった範囲があり、その周りには鍛冶炉とともに作業穴や水槽、金床を据えた穴と推測される施設が見つかっています。 このように、発見された鍛冶工房は操業時の姿がそのままの状態で残されており、当時の工人配置や作業工程の解明が期待できる貴重な資料といえます。 今回の調査では、鉄製品自体は出土していませんが、ここで何を製作していたのかを推測する手がかりが得られています。 工房内から木製の鍬の頭が複数点出土 しており、いずれも未使用であることから、鍬に装着する刃先を製作した可能性があります。 調査地は、豊臣氏大坂城南部の三の丸もしくは惣構の推定範囲内にあたり、南側の玉造一帯には諸大名の屋敷があったとされます。  規模が大きいこと、土木具である鍬の刃先などを製作していた可能性があること、大坂城外郭の軍事的に重要な地点に立地しているなどから、今回見つかった鍛冶工房は、大坂城の防御を目的とした土木工事に用いる道具などを製作するために設置されたと推測しています。 規模が大きいこと、土木具である鍬の刃先などを製作していた可能性があること、大坂城外郭の軍事的に重要な地点に立地しているなどから、今回見つかった鍛冶工房は、大坂城の防御を目的とした土木工事に用いる道具などを製作するために設置されたと推測しています。地中に残された痕跡から当時の工人の営みを復元していく上で、まだまだ判らないことがあります。現代の伝統工芸技術からも多くを学んでいきたいと考えています。 (大阪新刀の祖、「國貞」「國助」が大阪で活動を始めるのが元和の初め頃といわれています。時代は僅かに違いますが、ひょっとしたら此の地で、國助が刀を作ったのでは、とロマンを感じる発掘です。) 杉浦 記 |